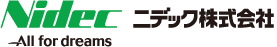2023年度特集 - 統合報告書2023
コーポレート・ガバナンス ― 強固なガバナンス体制の構築 ―
公正かつ透明性・実効性の高いガバナンス体制の実現
公正かつ透明性・実効性の高いガバナンス体制の実現
基本的な考え方
NIDECグループのコーポレート・ガバナンスの目的は、企業の誠実さを確立した上で社会の信頼を獲得し、「高成長、高収益、高株価」をモットーとした持続的な企業価値の拡大を図ることです。この目的のため、内部統制の維持・強化を通じて経営の健全性と効率を高めています。また、情報開示の充実を通じて経営の透明性を高めます。
取締役会の独立性と多様性の確保にも取り組んでおり、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや、職歴・性別・年齢等の多様性および事業規模に適した員数等を考慮しています。持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指す上で、コーポレート・ガバナンスは最重要課題の一つとして認識し、体制強化に取り組んでいきます。

2022年度の取り組み
取締役会の実効性確保については、毎年、社外取締役を含めた取締役会メンバーを対象にアンケートを実施し、実効性の評価と現状の課題分析をしています。また、客観的な評価・分析のため、2021年度より第三者(外部法律事務所)による評価の仕組みを導入しています。2022年度は、昨年度に引き続き取締役会の監督機能が高く評価されており、当社の取締役会は適切に機能していることを確認しました。引き続き本結果をもとに対応策を検討し、継続的な改善に務めていきます。
取締役および執行役員の選任方針・選任基準・候補者案の決定等に関して、2022年11月より取締役会の諮問機関として指名委員会を設置し、審議を行っています。2022年度は副社長5名の選任を行いました。
2023年度の役員報酬については、報酬委員会における審議を経た上で報酬水準の見直しを取締役会へ答申しました。
今後に向けて
取締役会の実効性確保については、各議題に係る情報の十分な提供や議論の機会の確保、ならびに業界情報やマーケット情報等の適切な事前提供が非業務執行取締役による事業理解促進に繋がります。したがって、代表取締役社長および事業本部長・業務執行役員他による事前説明会や非公式会合※について、その内容を充実させつつ継続実施する予定です。
指名決定のプロセスについては指名委員会が審議し、取締役会にて決議・明文化することで社内外、候補者への周知を可能とし、その公正性・透明性・客観性を高めることができています。2023年度は、2024年度の副社長の選任および、当社指名委員会初となる社長選任を行う予定です。また、報酬委員会の実効性についても引き続き向上させ、社会情勢やステークホルダーからの要請を勘案し、今後も必要な対応を進めていきます。
※ 経営戦略や事業の説明、現場見学の実施、投資家やその他のステークホルダーからの意見共有を行う会合
コーポレート・ガバナンスの変遷

コーポレート・ガバナンス体制


➊ 取締役会
運営状況
取締役会は、経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行います。経営に対する監督機能を強化し、経営の透明性・客観性を高めるため、独立性の高い社外取締役を選任しています。
取締役会の審議内容
取締役会の審議・報告内容(2022年度)

取締役会実効性評価アンケート(取り組みと評価)
実効性確保のため2022年度に実施した取り組み
- 社外取締役へ向けた事前説明を継続実施し、各案件情報の十分な提供、議論の機会を確保。
- 非公式会合における非業務執行取締役の事業理解促進(事業の説明・オンライン工場見学の実施)および投資家やその他のステークホルダーからの意見共有を継続的に実施。
- 投資案件等については中長期戦略目標との関係を取締役会で説明する等、情報展開を実施。
- 取締役選任時のスキルマトリクスの開示、業務上の責任者(執行役員等)選任時の、該当人物の経歴・スキル等の説明を継続的に実施。
2022年度の評価結果
- 取締役会の員数、構成(社内外役員割合・多様性等)、頻度、時間、情報の質と説明に加え、「総じて取締役会は十分に機能している」、「取締役会資料には必要な情報が網羅されている」、「取締役会は、経営層の後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう十分に監督が行えている」との点で評価を得た。
- 第三者(外部法律事務所)からも、取締役会の実効性については、取締役会の構成面・運営面をはじめとして全般的に高く評価されており、取締役会において充実した議論が行われる体制が整備され、現に自由闊達で充実した議論が行われていることを確認。また取締役会の監督機能全般についても高く評価されており、また、近時、重要な経営課題との意識が高まっているサステナビリティ等についても充実した議論がなされていることが確認された。なお、この第三者による評価の仕組みは2021年度より導入している。
- 課題点としては、取締役会資料の提供時期について早期化を求める指摘が複数寄せられ、また、中長期的な経営戦略・課題に関してより議論を深めるべきとの指摘もなされており、さらなる改善が求められるものと考えられる。

スキルマトリクス

➋ 監査等委員会
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査人から監査報告を受けます。
委員構成および議長の属性

監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会と会計監査人との間で、四半期ごとの会合に加え、年に2、3回ほど必要に応じ会合を行っています。会合では監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っています。
監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部監査部門である経営管理監査部により、定期的に監査等委員会に対する報告会が実施されており、監査等委員会はNIDECグループにおける内部監査の結果につき報告を受けています。また、監査等委員会は経営管理監査部との間で必要に応じて意見交換、情報共有を行い、経営管理監査部に対し実地監査の要請を行っています。
➌ 指名委員会
社外取締役酒井貴子が委員長を務め、社内取締役2名、社外取締役3名で構成されています。取締役および執行役員等の選任方針・選任基準や継承プラン・サクセッションプランの考え方、副社長の候補者案、社長候補者案の決定に向けた取り組み等を審議しています。
➍ 報酬委員会
代表取締役社長執行役員(最高執行責任者)小部博志が委員長を務め、社内取締役2名、社外取締役3名で構成されています。役員報酬に係る基本方針や報酬体系等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申します。
取締役報酬方針
1. 基本方針
当社の役員報酬は、グローバルな競争力の強化と事業の持続的な成長を目的とし、以下の方針に基づいて決定されます。
- 企業価値向上へのモチベーションを高めるものであること
- 優秀な経営人材確保に資するものであること
- 当社の企業規模と事業領域において適正な水準であること
2. 報酬構成の概要
- 社外取締役(監査等委員である取締役を除く)
固定報酬 - 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)
固定報酬:変動報酬(賞与):業績連動型株式報酬
=3:1.5:1

3. 報酬の決定プロセス
役員(監査等委員である取締役を除く)の個人別の固定報酬および変動報酬の額については、本方針に定める基準に従って、任意の諮問機関である報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定します。また、業績連動型株式報酬の内容についても、同様に報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定します。
4. 報酬の没収等(クローバック・マルス)
固定報酬および変動報酬については、会社に重大な損害を与えた場合は、対象者の同意を得て減額することがあります。
また、業績連動型株式報酬については、受益権確定日以降、株式交付対象者が職務や社内規程への重大な違反等の非違行為があった場合、会社は、その者に対して賠償を求めることができます。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

※1 上記業績連動型株式報酬には、第48期中に退任した取締役2名及び50期中に退任した1名分を含んでいます。
※2 2018年6月20日開催の第45期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決議されています。上記は日本基準により当事業年度に費用計上した金額を記載しています。なお、社外取締役は制度の対象外となっています。
役員ごとの連結報酬等の総額等

※ 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
➎ 各種委員会

➏ 経営会議
経営会議は月1回開催され、月次決算の総括や、管理部門、関係会社、事業本部等の重要事案を全社横断的に審議する会議により業務執行状況を把握するとともに、以降の業務執行についての判断を行います。
➐ Management Committee
Management Committeeは代表取締役会長の諮問機関として原則月2回開催され、代表取締役社長が議長を務め、全般的業務執行方針や計画の審議および個別重要案件の審議を行います。
社外取締役選任理由および主な活動状況

※1 当事業年度における取締役会の開催回数は26回、監査等委員会の開催回数は14回、指名委員会の開催回数は3回、報酬委員会の開催回数は1回です。
※2 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
※3 2022年6月17日開催の第49期定時株主総会において、酒井貴子氏は取締役に就任しました。同氏はそれ以前、当社の取締役(監査等委員)として取締役会、監査等委員会、報酬委員会に出席していたため、同氏の出席回数は取締役(監査等委員)として出席した回数を含んでいます。
社外取締役のサポート体制
社外取締役については、取締役会事務局である総務部が補佐しています。通常の業務連絡等を通じてタイムリーな会社情報を提供し、各種問い合わせに対応するとともに、取締役会の開催に際しては全取締役に対し開催日前日までに取締役会の議案関連資料および経理情報を提供しています。加えて、監査等委員である社外取締役については、内部監査部門である経営管理監査部が補佐しています。監査等委員会の開催に際しては、全監査等委員に対し開催日3日前までに開催の通知をするとともに、監査等委員会の議案関連資料を前日までに事前送付しています。監査等委員会後は議事録を作成、全監査等委員に対し送付しています。また社外取締役である監査等委員に対しては、必要に応じて監査等委員会等で常勤監査等委員や当社役員等から各種情報が随時報告・提供されています。
なお、監査等委員以外の社外取締役と監査等委員の間で非公式会合を開催しています。非公式会合では当社役員等から各種情報が提供されているほか、直接訪問またWebを活用した方式で国内事業所の視察を実施しています。
内部統制
基本的な考え方
NIDECグループは、国内証券取引所上場企業に求められるコンプライアンス体制を確立し、リスク管理責任を明確化することにより経営の健全性・透明性の向上に努めます。具体的には、経営管理監査部の監査活動により、金融商品取引法第24条の4の4第1項が求める財務報告における内部統制の有効性の維持と改善を図ります。また、取締役会の下にコンプライアンス委員会・リスク管理委員会・情報セキュリティ委員会およびCSR委員会を組織し、それぞれの事務局として法務コンプライアンス部・リスク管理室・情報システム部およびIR・CSR推進部を設置し、内部統制のための企業風土づくり・管理体制の強化に対応しています。

2022年度の取り組み
2025年度売上高4兆円を前提にした実効性の高いグローバル内部監査体制を確立するためには、内部監査業務の高度化と効率化が不可欠です。今年度は、現場レベルにおける自主監査体制の強化(NIDECグループの全拠点)およびDXの活用による総連結を対象にしたモニタリングの実施により、財務報告に係るエラーの未然防止やリスク領域の見える化と監査手続の深化に取り組みました。
今後に向けて
DXを活用した監査業務の高度化と効率化は、対象領域を拡大して引き続き実施していきます。また、専門資格や語学力を有し、ビジネス環境を深く理解する監査員を育成する等、人材の高度化に注力していきます。現在は日本(京都)・欧州(アムステルダム)・米州(セントルイス)・中国(上海)・アジア(シンガポール)の5拠点に監査体制を構築し、NIDECグループをカバーしていますが、会社数の増加が顕著な欧州地区の監査体制の強化にも取り組んでいきます。
グループ会社のコーポレート・ガバナンス
NIDECグループ会社は、当社の経営理念や方針のもと活動を行っており、当社の内部統制体制の中に組み込まれています。なお、当社からグループ会社に対し、役員の派遣、従業員の出向を行っていますが、各グループ会社は専門家等の意見も踏まえ、十分に議論を尽くした上で各社の実情に対応した業務執行の意思決定を行うなど、その独立性の確保に努めています。
政策保有株式
政策保有株式に関する方針
当社は、事業上やその他分野で取引・協力関係のある企業と将来にわたり取引・協力関係の維持・強化を図ることで中長期的な観点から事業の安定化などを通じ当社の企業価値向上に資すると期待される株式を保有しています。なお、個々の政策保有株式については、毎年取締役会において、保有目的等の定性面に加え、保有に伴う便益などを経済合理性の観点から定量的に検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については縮減を図ります。
政策保有株式の議決権行使の基準
当社は、政策保有株式に係る議決権行使にあたって、投資先企業の持続的成長に資することを基本方針とし、コーポレート・ガバナンス整備状況およびコンプライアンス体制なども総合的に勘案の上、適切に議決権を行使します。
(議決権行使の基本的な考え方)
投資先の個々の株主総会議案については、中長期投資の視点で取引・協力関係の維持・強化という株式保有の目的に資するかどうかという観点を含め、特に重要な資産の譲渡・合併等の組織再編等のような株主価値の毀損につながる事象に関し、個別に確認を行った上で議案の賛否について判断します。なお、法令違反や反社会的行為に該当する議案については、事情の有無を問わずに反対します。